政策観測室|最終更新:2026年1月15日
住宅ローン:金利が0.5/1.0/2.0%上がると毎月返済はいくら増える?(元利均等・即時計算)
物価・エネルギー・金利と、家計の固定費に波が続いています。本稿では、金利が 0.5%・1.0%・2.0% 上がると返済がどれだけ増えるかを、元利均等返済で瞬時に可視化。固定切替・借換え・繰上げ返済の意思決定に役立つよう、シミュレーター・事例計算・チェックリストまで整理します。
要点まとめ(3分で把握)
- 元利均等では金利上昇=毎月返済の増加に直結。借入が大きい/期間が長いほど増分は大きい。
- 経験則:+1.0%の金利上昇で、3,500万円・35年なら月約+1.7万円前後が目安(条件により差)。
- 固定切替は「何%まで耐えられるか」で判断。可処分に占める返済比率(DPI比)を確認。
- 繰上げは早期×期間短縮型が利息減に効く。ボーナス返済の偏りに注意。
編集方針:中立・一次資料重視。最終更新:2026年1月15日
1. 金利と返済の基本(元利均等)
元利均等返済の毎月返済額 M は、元金 P、年利 r(月利 i = r/12)、返済回数 n(年×12)で下式:
M = P × { i(1+i)n / [(1+i)n − 1] } (i = r / 12)
直感的には、金利↑・期間↑・元金↑で毎月返済は増加。金利感応度は借入初期ほど高い傾向です。
2. かんたん試算ツール(毎月返済・総利息・金利上昇耐性)
数値は半角・全角・カンマ・「万」表記OK(例:3,500万)。+0.5 / 1.0 / 2.0%のクイック比較と、現行±2%を0.25%刻みで一覧表示します。
3. 事例で比較:3,500万円・35年・0.9%→1.9%・2.9%
下の表は本ツールで算出した概算例です(端数処理あり)。ページ読み込み時に自動で表示されます。
| 金利 | 毎月返済(概算) | 増減(月) | 総利息(概算) |
|---|---|---|---|
| 0.90% | — | 基準 | — |
| 1.90% | — | — | — |
| 2.90% | — | — | — |
4. 判断の物差し:返済比率・固定化・繰上げ
返済比率(DPI比)
手取り収入に占める返済額の割合。目安は25%以下、最大でも30%台前半に収めると安定。家族構成の変化(教育費・介護)も織り込む。
固定化の考え方
「何%まで耐えられるか」を先に決め、閾値に達したら固定へ一部スイッチ。全額固定にこだわらず、ミックスで分散も有効。
繰上げ返済
早期×期間短縮型が利息カットに効く。手元流動性は6〜12か月分の生活費を死守。NISA/社保・税の控除とトレードオフも要チェック。
5. よくある質問(FAQ)
Q1. 変動が上がったらすぐ固定へ?
「上がったから固定」ではなく、自分の耐性ラインに達したら検討。金融機関・手数料・団信・借換えコストを含む総合判断を。
Q2. 借換えはいつが得?
差額返済と諸費用の回収年数(損益分岐)を試算。3〜5年で回収できるなら有力。返済残期間が短いと効果は逓減。
Q3. ボーナス返済は有利?
偏りが大きいと金利上昇局面で資金繰りリスク。毎月返済中心+臨時繰上げの方が安全です。
6. 出典・参考リンク(公的・一次情報)
- 金融庁:住宅ローンの基礎知識・金利タイプ
- 住宅金融支援機構(フラット35):金利情報・返済シミュレーション
- 各銀行:金利・手数料・団信・借換え条件の比較ページ
※本記事は一般的な情報提供です。実行条件・個別事情で結果は変わります。最終判断は各金融機関の最新情報でご確認ください。
更新履歴
- 2026年1月15日:記事公開。シミュレーター初期値を「3,500万円・35年・0.9%」に設定。
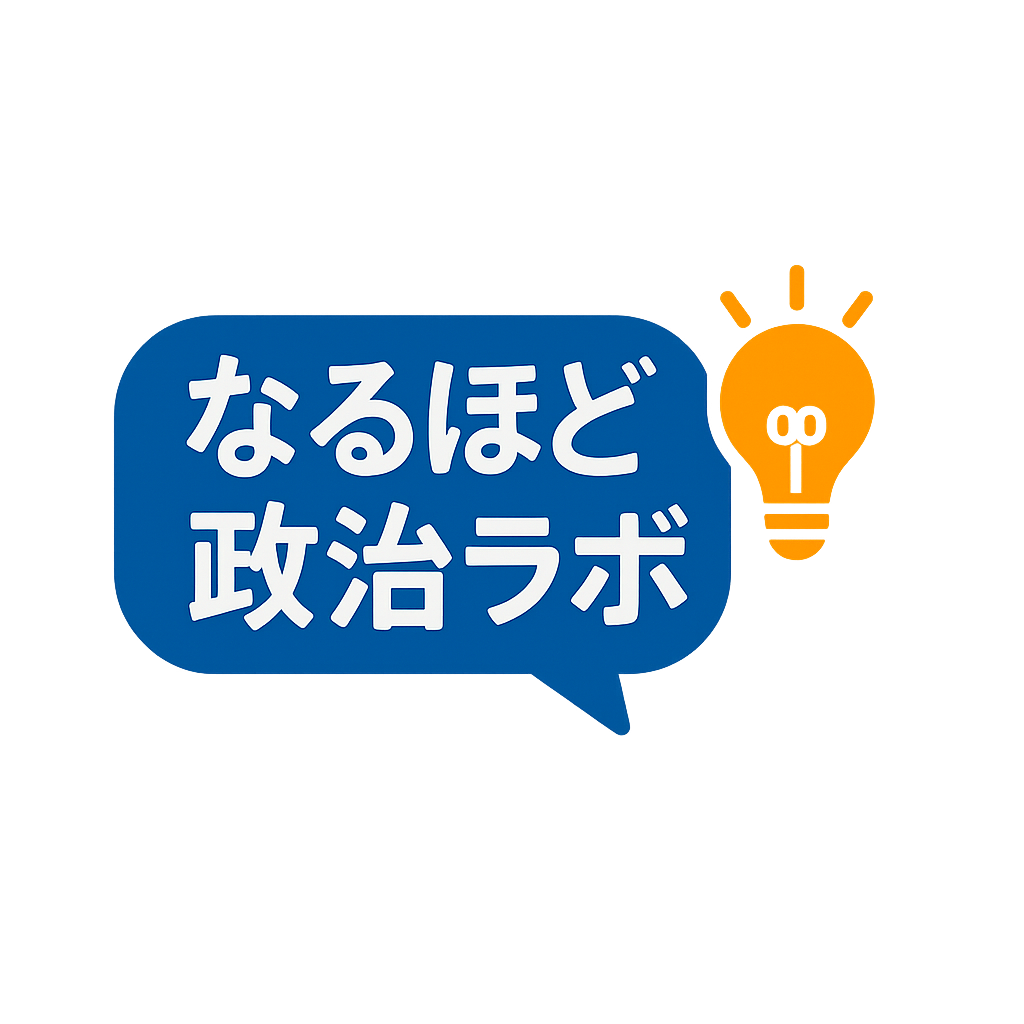
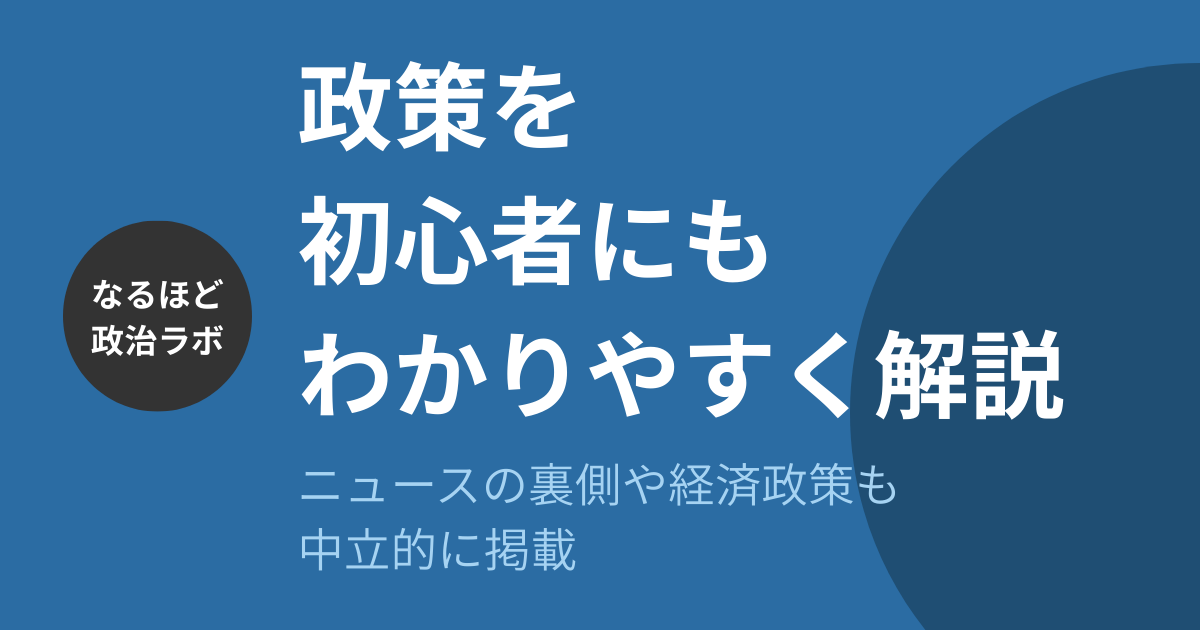
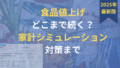
コメント